大地震や台風などの災害発生時、SNSやインターネット上では様々な情報が飛び交います。しかし、その中には真偽不明なデマ情報も多く含まれており、注意が必要です。デマ情報を信じてしまうと、混乱を招いたり、二次的な被害に繋がる可能性もあります。今回は、災害時に注意すべきデマ情報とその対策について解説します。
災害時に拡散しやすいデマ情報とは?
災害時には、人々の不安や恐怖につけ込んで、様々なデマ情報が拡散されます。代表的なものをいくつかご紹介します。
- 特定の場所で火災が発生した
- 〇〇で感染症が流行している
- 〇〇に強盗や略奪が入った
- 〇〇に毒物/有害物質がばらまかれた
- 政府や自治体が〇〇を隠蔽している
これらの情報は、人々の不安を煽り、パニックを引き起こす可能性があります。
デマ情報に惑わされないために、私たちができること
デマ情報に惑わされないためには、以下の点に注意することが重要です。
- 情報の出所を確認する
- 公的機関(気象庁、自治体など)や報道機関など、信頼できる情報源からの情報を確認しましょう。
- SNSなどで拡散されている情報は、発信元が不明な場合や、信頼性に欠ける場合があります。
- 複数の情報を照らし合わせる
- 一つの情報だけでなく、複数の情報源から情報を収集し、内容を照らし合わせることで、情報の正確性を判断しやすくなります。
- 感情的な情報に注意する
- 過度に不安を煽るような情報や、感情的な言葉で書かれた情報は、デマである可能性が高いです。冷静に情報を判断するようにしましょう。
- 情報を安易に拡散しない
- 情報の真偽が不明な場合は、安易に拡散しないようにしましょう。デマ情報の拡散は、混乱を広げるだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
- 公的機関の情報を確認する
- X(旧Twitter)などのSNSで各公的機関のアカウントをフォローしたり、防災アプリなどを活用して、公的機関からの正確な情報をいち早く入手できるようにしましょう。
もしデマ情報を発見したら
もしデマ情報を発見したら、以下の対応をしましょう。
- 情報を拡散しない
- 情報の出所に注意喚起する
- 公的機関に通報する
デマ情報の拡散を防ぐためには、一人ひとりの意識が重要です。
情報リテラシーを高め、災害に備えよう
災害時には、正確な情報を迅速に入手することが重要です。そのためには、普段から情報リテラシーを高め、情報の真偽を判断する力を養っておくことが大切です。
参考情報
情報の洪水に流されず、正しい情報を選択し、安全な行動を心がけましょう。
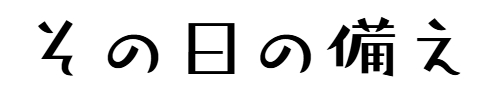






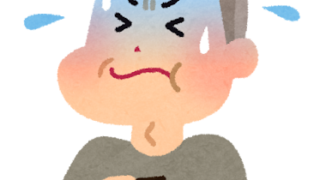




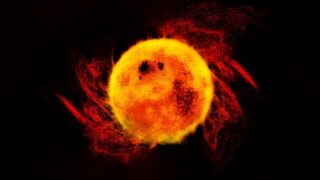
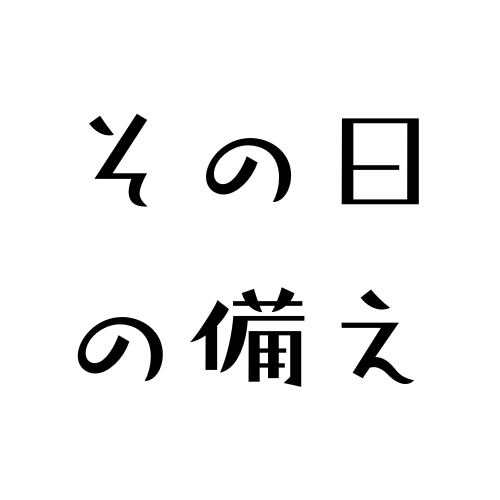
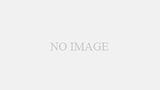
コメント