地震大国である日本において、沿岸部で特に警戒すべき災害の一つに津波があります。津波から命を守るために、古くから語り継がれている言葉に「津波てんでんこ」があります。この言葉は、一見すると利己的に聞こえるかもしれませんが、津波から命を守るための重要な教訓を含んでいます。
今回は、「津波てんでんこ」の言葉の意味や、いつ頃からこの言葉が使われるようになったのか、また、私たちが日頃から意識しておくべきことについて解説します。
「津波てんでんこ」とは?
「津波てんでんこ」とは、津波が発生した際には、周囲の人に構わず、各自が自分の判断で高台などの安全な場所へ避難するという教えです。
「てんでん」とは、三陸地方の方言で「各自バラバラに」という意味です。つまり、「津波てんでんこ」は、「津波が来たら、各自バラバラに逃げろ」という意味になります。
「津波てんでんこ」が生まれた背景
三陸地方は、過去に何度も津波による甚大な被害を受けてきました。その経験から、「自分の命は自分で守る」という意識が根付き、「津波てんでんこ」という言葉が生まれたと考えられています。
この言葉は、明治時代から存在していたと言われており、1990年11月に岩手県下閉伊郡田老町(現・宮古市)にて開催された第1回「全国沿岸市町村津波サミット」において、同様の意味で東北の三陸地方で昔から伝えられてきた「津波起きたら命てんでんこだ」に由来する「命てんでんこ」という言葉が生まれたという説もあります。
2011年の東日本大震災では、「津波てんでんこ」の教えが多くの人の命を救ったと言われています。
「津波てんでんこ」の真意
「津波てんでんこ」は、決して利己的な考え方ではありません。津波は非常に速いスピードで沿岸に押し寄せるため、一人でも多くの人が助かるためには、各自が迅速に避難する必要があります。
もし、誰かを待っていたり、助けようとしていたら、自分だけでなく、その人も命を落としてしまうかもしれません。「津波てんでんこ」は、結果的に多くの人の命を救うための、合理的な判断なのです。
私たちが日頃から意識しておくべきこと
- 避難場所と避難経路の確認:
- 自宅や職場、学校など、自分がよくいる場所から最寄りの避難場所と避難経路を確認しておきましょう。
- 避難訓練への参加:
- 自治体や学校などで実施される避難訓練に積極的に参加し、避難行動を身につけましょう。
- 情報収集:
- テレビやラジオ、インターネットなどで、津波に関する情報を収集しましょう。
- 家族との安否確認方法の確認:
- 災害時に家族と連絡が取れるように、安否確認の方法を決めておきましょう。
「津波てんでんこ」の教えを胸に、日頃から津波への備えを怠らないようにしましょう。
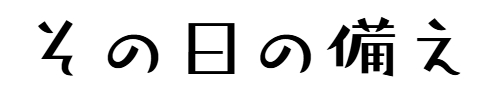


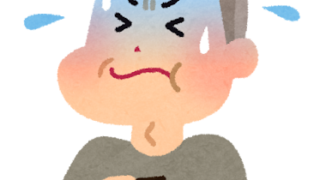



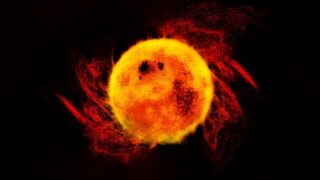





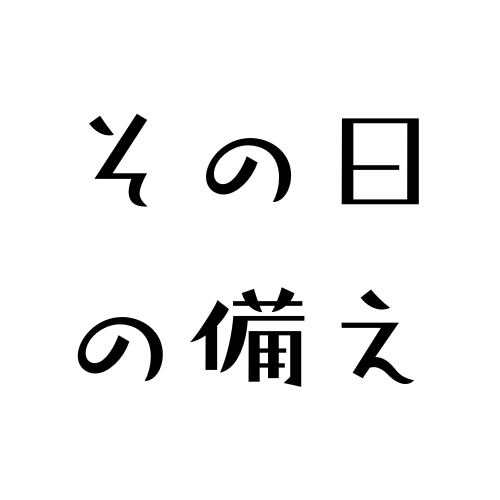
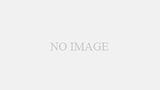
コメント