近年、高齢化が進み、一人暮らしの高齢者の方が増えています。もしもの災害時、ご自身での避難や安全確保が難しい場合もあり、離れて暮らす家族としては心配が尽きないものです。今回は、高齢の一人暮らしの親御さんのために、私たち家族ができる防災対策と、地域社会への協力依頼について具体的にご紹介します。
離れて暮らす家族ができる防災対策
直接的な介助が難しい離れた場所に住む家族でも、様々な形で親御さんの防災をサポートできます。
- 防災用品の準備と定期的な見直し
- 親御さんの状況に合わせて、非常食、飲料水、懐中電灯、ラジオ、救急セット、常備薬などを準備し、定期的に賞味期限や電池残量を確認しましょう。
- 持ち運びやすいリュックサックにまとめておくと、避難時にも便利です。
- 必要に応じて、簡易トイレや暖を取るためのブランケットなども用意しましょう。
- 緊急連絡先のリスト作成と共有
- 親御さんの緊急連絡先(かかりつけ医、近隣の親戚・友人、地域の民生委員など)をリスト化し、親御さんの見やすい場所に保管するとともに、家族間でも共有しておきましょう。
- 避難場所と避難経路の確認
- 親御さんの自宅から最寄りの避難場所や、安全な避難経路を一緒に確認しておきましょう。可能であれば、実際に歩いてみるのも良いでしょう。
- バリアフリーに対応した避難場所や、福祉避難所の情報も把握しておくと安心です。
- 安否確認の方法とタイミングの決定
- 災害発生時の安否確認の方法(電話、メッセージアプリなど)と、連絡を取り合うタイミングを事前に決めておきましょう。災害用伝言ダイヤル「171」の利用方法も共有しておくと良いでしょう。
- 防災情報の共有と理解のサポート
- 地域のハザードマップや防災情報、気象警報・注意報などを親御さんに分かりやすく伝え、内容を理解してもらうように努めましょう。
- スマートフォンをお持ちでない場合は、ラジオの活用方法などを伝えましょう。
- 家具の固定と安全な居住環境の整備
- 親御さんの自宅の家具が転倒しないように固定したり、落下する可能性のある物を低い場所に移動するなど、安全な居住環境を整えましょう。
- 割れたガラスによる怪我を防ぐために、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼るのも有効です。
- 定期的な連絡と声かけ
- 日頃から電話やオンライン通話などで定期的に連絡を取り、体調や生活状況を確認するとともに、防災に関する話題にも触れ、意識を高めてもらいましょう。
地域への協力依頼:見守りネットワークの構築
離れて暮らす家族だけでなく、地域社会の協力も高齢者の方の安全確保には不可欠です。
- 自治会・町内会への情報提供と連携
- 親御さんが一人暮らしであること、災害時に支援が必要となる可能性があることを自治会や町内会に伝えておきましょう。
- 地域の防災訓練に親御さんが参加できるよう促したり、参加が難しい場合は、代わりに家族が地域の防災活動に参加し、情報を共有するのも良いでしょう。
- 民生委員・福祉協力員への相談
- 地域の民生委員や福祉協力員は、高齢者の方の見守りや支援を行っています。親御さんの状況を伝え、日頃の見守りや災害時の支援について相談してみましょう。
- 近隣住民への声かけのお願い
- 親御さんの近隣に住む方に、日頃から声かけや見守りをお願いしておくと、万が一の際に早期発見や安否確認につながる可能性があります。
- 地域の防災ボランティアへの協力依頼
- 地域には、災害時に高齢者や障がい者などの支援を行う防災ボランティア団体が存在する場合があります。事前に情報を収集し、必要に応じて連携をお願いしてみましょう。
- SOSネットワークの構築
- 親御さんの自宅に、緊急時に助けを求めるためのサイン(黄色いハンカチを窓に掲示するなど)を決めておき、近隣住民や関係者に共有しておくのも有効です。
地域の力を借りながら、できる限りの備えを
高齢の一人暮らしの方の防災対策は、ご本人だけでなく、家族や地域社会全体で取り組む必要があります。できることから少しずつ始め、連携を強化することで、もしもの時に大切な命を守れるように備えましょう。
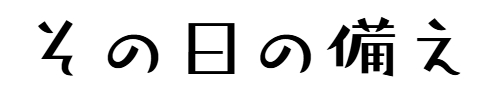









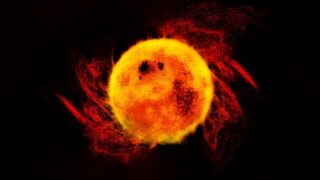

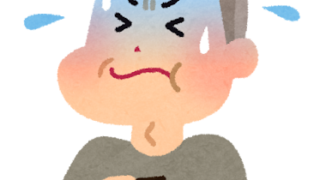
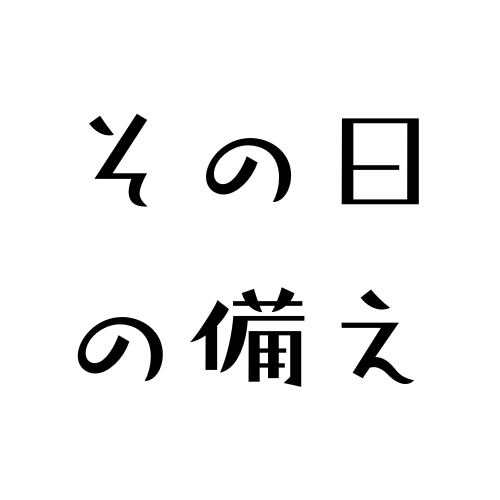
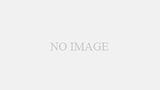
コメント