「フェーズフリー防災」という言葉、あまり聞きなれない方もいるかもしれませんが、今後よく聞く言葉になるはずです。これは、災害への備え方に関する新しい考え方で、注目を集めています。今回は、フェーズフリー防災とは何か、具体的な例も交えながら分かりやすく解説します。
フェーズフリー防災ってなに?
フェーズフリーとは、「日常時」と「非常時」という2つの状態(フェーズ)を分けずに考えることです。つまり、普段から使っているものが、もしもの災害時にも役立つように考えて、モノやサービスを選ぶという考え方です。
これまでの防災は、「災害が起きた時のために特別な備えをする」という考え方が主流でした。しかし、フェーズフリー防災では、「普段の生活で使うモノを、災害時にも使えるものにする」ことで、特別な備えをしなくても自然と災害に備えることができます。
なぜフェーズフリー防災が注目されているの?
- 備蓄の負担軽減: 非常時だけしか使わないモノを保管するスペースや手間が省けます。
- 心理的なハードルを下げる: 普段使っているモノが役立つので、防災を「特別なこと」と感じずに済みます。
- 生活の質向上: 日常生活で便利なモノを使うことが、災害時の安心にもつながります。
どんなものがフェーズフリー?
具体的にどんなモノや考え方がフェーズフリーにあたるのか、例を見てみましょう。
- モバイルバッテリー: 普段からスマホなどの充電に使っているモバイルバッテリーは、災害時の情報収集に不可欠なスマホを充電するためにも役立ちます。
- カセットコンロ: 普段の料理に使うカセットコンロは、災害でライフラインが止まった際にも温かい食事を作るために役立ちます。
- レインコート: 雨の日に着るレインコートは、災害時の雨風を防ぐだけでなく、防寒具や簡易的な目隠しとしても活用できます。
- スニーカー: 普段履いている歩きやすいスニーカーは、災害時の避難や移動に役立ちます。
- ラジオ付きスマートフォン: 普段の音楽や情報収集に使うスマートフォンは、災害時にはラジオとして情報を得る手段になります。
考え方もフェーズフリーに
モノだけでなく、行動や考え方もフェーズフリーにすることができます。
- ウォーキングコースに避難場所への道順を取り入れる: 普段の運動が、いざという時の避難訓練になります。
- ローリングストック: 普段から少し多めに食品を買い、賞味期限の近いものから消費して買い足すことで、常に一定量の備蓄がある状態を保つことができます。
まとめ
フェーズフリー防災は、私たちの生活の中に無理なく防災を取り入れられる、賢い考え方です。普段の生活を見直して、フェーズフリーなモノや考え方を取り入れてみてはいかがでしょうか。
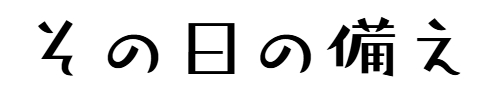




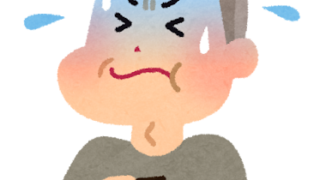



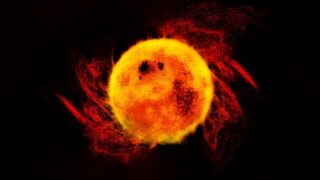




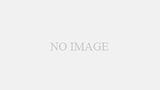
コメント