「晴れていたのに急に空が真っ暗になって、ゴロゴロと雷の音が響き渡り、氷の塊が降ってきた!」そんな経験はありませんか? これは「雹(ひょう)」と呼ばれる気象現象です。小さくても当たると痛い雹ですが、大きさによっては甚大な被害をもたらすこともあります。
今回は、雹の痛みレベル、発生時期、なぜ気温が高い時期でも雨にならないのか、そして雹の発生メカニズムまで、雹の謎を徹底的に解き明かします。
雹(ひょう)ってどんなもの?あられとの違いは?
雹(ひょう)は、積乱雲の中で作られる直径5mm以上の氷の塊です。あられは、同じく積乱雲内で生成される氷の粒ですが、直径が5mm未満である点が雹との大きな違いです。また、雹は層状の構造を持っていることが多いのに対し、あられは構造が不透明で層状になっていません。
雹やあられが降りやすい時期は?
雹は一年を通して発生する可能性がありますが、特に発生しやすい時期が2つあります。
- 春から初夏(3月~5月、6月~8月): この時期は、寒気と暖気がぶつかり合い、積乱雲が発達しやすい環境です。また、日中の気温上昇によって大気の状態が不安定になることも、雹の発生を助長する要因となります。
- 夕立の多い時期: 夏季の夕立も、積乱雲が発達することで発生します。そのため、夕立とともに雹が降ることも珍しくありません。
なぜ気温の高い時期でも雨ではなく雹が降るのか?
気温が高い時期に雨ではなく雹が降るのは、積乱雲の中の気温と気流が大きく関係しています。
積乱雲の上部では、気温が氷点下になるほど冷え込んでいます。この上空で水滴が凍り、氷の粒(氷晶)となります。そして、積乱雲内には強い上昇気流が吹いています。この上昇気流に乗って、氷晶は何度も上空へと運ばれ、その過程でさらに水滴を付着させて凍り、大きくなっていくのです。
つまり、地上付近の気温が高くても、積乱雲の上空が氷点下であること、そして強い上昇気流が存在することが、雹が降るための重要な条件となります。
雹が発生する驚くべきメカニズム
雹は、積乱雲の中で以下のような複雑なメカニズムを経て発生します。
- 強い上昇気流の形成: 積乱雲の中では、暖かく湿った空気が急激に上昇する「上昇気流」が形成されます。この上昇気流が、雹の材料となる水滴を上空へ運び上げます。
- 氷晶核となる塵や粒子: 上空で水滴が凍るためには、氷晶核となる微小な塵や氷の粒子が必要です。これらの粒子は、大気中に浮遊しており、水滴が触れると凍結を促進します。
- 凍結と成長の繰り返し: 氷晶核となった氷粒は、上昇気流によって何度も上空へと運ばれ、その過程でさらに水滴を付着させて凍結し、徐々に成長します。この成長の過程で、雹は層状の構造を持つことが多いです。
- 落下: 成長して重くなった雹は、ついに上昇気流に支えきれなくなり、重力によって地上へと落下します。
積乱雲の中で上昇気流が発達しているほど、雹は大きく成長しやすくなります。直径が数センチメートルを超えるような巨大な雹が降ることもあります。
雹に当たるとどれくらい痛い?
雹の大きさや落下速度によって、痛みや危険度は大きく異なります。
- 小粒の雹: 小さなあられのような雹であれば、パチパチと当たる程度の痛みで済むことが多いです。
- 大粒の雹: 直径が1cmを超えるような雹になると、落下速度も増し、体に当たると強い痛みを感じます。
- 巨大な雹: 直径が数センチメートルを超えるような雹は、非常に危険です。時速100kmを超える速さで落下することもあり、人に当たると大きな怪我をすることがあります。車がへこんだり、窓ガラスが割れたりすることもあります。
雹から身を守るための対策
雹の可能性がある場合は、気象情報に注意し、以下の対策を心がけましょう。
- 頑丈な建物の中に避難する: 雹が降ってきたら、できるだけ早く建物の中に避難しましょう。
- 外出を控える: 雹の可能性がある場合は、不要不急の外出は控えましょう。
- 車での移動は慎重に: 運転中は、急な視界不良や道路の状況変化に注意しましょう。
- 身を守る: 屋外で避難場所がない場合は、姿勢を低くして頭部を保護しましょう。
まとめ
雹は、積乱雲の発達によって発生する気象現象であり、時に大きな被害をもたらすことがあります。雹のメカニズムや危険性を理解し、適切な対策を行うことで、雹による被害を最小限に抑えましょう。
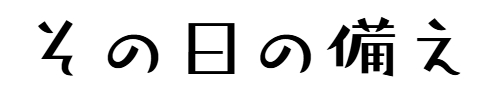





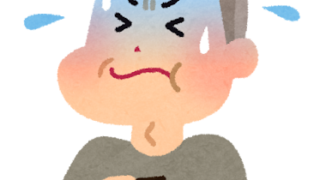


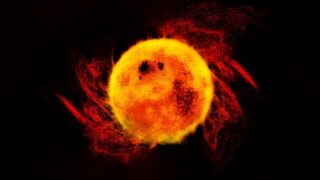



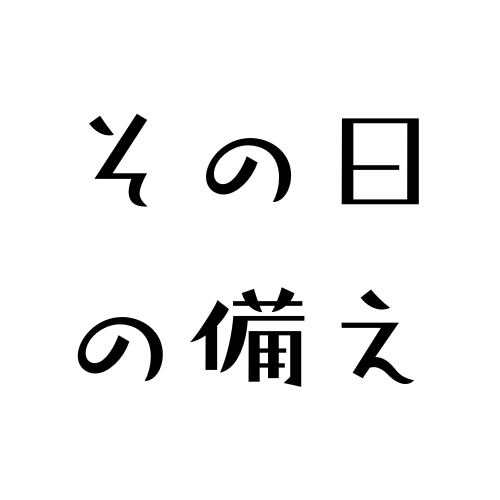
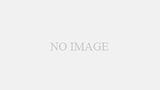
コメント