春風に舞う桜吹雪。川面に映る淡いピンクの桜並木は、日本の春を象徴する美しい風景です。でも、ふと疑問に思ったことはありませんか?なぜ、こんなに多くの桜が川沿いに植えられているのでしょうか?実は、その理由は、見た目の美しさだけではない、昔の人々の知恵と防災への想いに深く関わっているのです。
江戸時代に生まれた「桜堤」という防災対策
川沿いに桜並木が多いのは、江戸時代に始まった「桜堤(さくらづつみ)」という治水対策が大きく影響しています。当時の人々は、度々起こる洪水の被害に悩まされていました。そこで、考え出されたのが、桜の木を堤防に植えるという画期的なアイデアだったのです。
- 桜の根が堤防を強くする 桜の木は、地中深くまでしっかりと根を張り巡らせる性質があります。この根が、堤防の土をしっかりと固定し、大雨や洪水による土砂の流出を防ぐ役割を果たしました。
- 「お花見」が堤防を強化する 春になると、多くの人々が桜を見に堤防を訪れます。花見客が堤防の上を歩き、土を踏み固めることで、堤防の強度が増し、決壊しにくくなると考えられたのです。
先人の知恵が現代に伝える防災意識
美しい桜並木は、まさに先人の知恵と、災害から人々を守ろうとする強い想いの結晶だったのです。
現代では、コンクリートなどで強固な堤防を築く技術がありますが、桜並木は、以下のような形で、現代の防災にも貢献しています。
- 防災意識の向上 桜並木は、多くの人々に親しまれ、愛される存在です。桜を見ることで、川や堤防への関心が高まり、水害に対する防災意識の向上につながる可能性があります。
- 地域のコミュニティ形成 花見の場として、多くの人が集まる桜並木は、地域住民の交流を促進し、コミュニティの結束を強める役割も果たします。災害時には、地域住民同士の助け合いが非常に重要になります。
桜と生きる、持続可能な社会
桜並木は、自然と共生しながら、災害を防ぐという、持続可能な社会のあり方を示唆しているとも言えるでしょう。
来年のお花見では、桜の美しさを愛でるとともに、その背景にある歴史や防災への想いにも、少しだけ思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
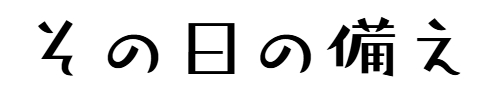

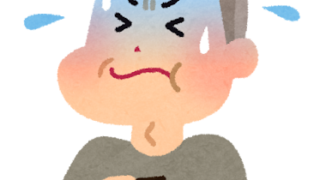





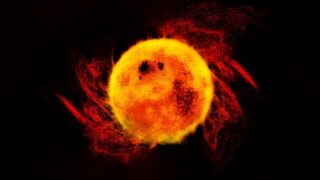




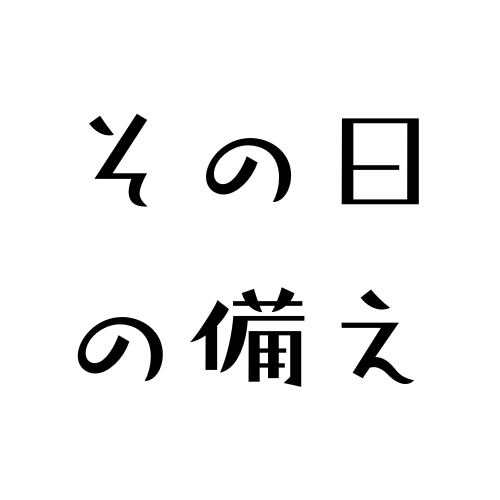
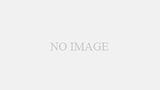
コメント